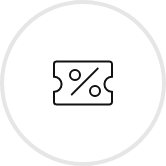開発担当者に聞く!にちにち道具 ごはん鍋が叶える、丁寧なごはん体験
日本人にとって、毎日の食卓に欠かせない「ごはん」。
ふっくらと炊きあがった白米の香り、一粒一粒の輝き・・・みんな大好きですよね。
2025年秋に新発売となる「にちにち道具のごはん鍋」
「お米が貴重な食材となりつつある今だからこそ、その本来の美味しさを最大限に引き出す道具をお届けしたい」
そんな想いから、信楽の土で作った、にちにち道具の「ごはん鍋」は生まれました。
今回は、このごはん鍋の開発を担当するブランドマネージャーのyamanakaさんに、誕生までの道のりと、そこに込められた想いを聞きました。

理想は「粒立ちが良く、ふっくら甘い」ごはん
morita:そもそも、なぜ土鍋の「ごはん鍋」を作ろうと思われたのですか?
yamanaka: 日本人にとって「ごはん」はやはり特別な存在ですよね。だからこそ、お米本来の美味しさを存分に味わえる最高の道具を作りたい、と考えたのが始まりです。
日本のやきものは世界で最も長い歴史を持っています。土鍋特有の高い蓄熱性を活かせば、きっと理想のごはんが炊けるはず。それは、私たちが大切にしている「丁寧なくらし」をまさに体現するアイテムだと思いました。
morita:目指した「理想のごはんの味」とは、どのようなものでしたか?
yamanaka:土鍋で炊いたからこそ感じられる、「お米の一粒一粒がしっかりと立ち、噛むほどにふっくらとした甘みが広がるごはん」です。
でも、「土鍋でごはんを炊くのは火加減が難しそう…」と、ハードルが高いと感じる方も少なくありません。だからこそ、誰でも手軽に、自分好みの硬さの美味しいごはんが炊ける。そんな「ごはん体験」をしてもらいたいと強く思っていました。

“使う人”に寄り添った、こだわりのデザイン
morita:にちにち道具のごはん鍋は、他とどう違うのでしょうか?こだわりのポイントを教えてください。
yamanaka:最もこだわったのは、毎日使う道具としての「扱いやすさ」です。
一般的な土鍋だと、熱くなった蓋を鍋つかみで持とうとしても、つまみが小さくてしっかり掴めず、不安に感じることがありました。そこで、にちにち道具のごはん鍋は、しっかりと掴める大きな本体の持ち手と、くびれがあって掴みやすい形の蓋のつまみを採用しました。

機能面では、お米が鍋の中でしっかり対流するように、内側は丸みを帯びた形状に。さらに、何度も試作を重ねて蓋の重さや形を調整し、内蓋がなくても吹きこぼれにくい設計を実現しました。
morita:見た目も、一般的な土鍋とは少し違う印象です。
yamanaka:土鍋というと飴釉や黒色のものが多いですが、私たちはにちにち道具らしい上質さを表現したかったんです。選んだのは、深みのある「黒飴釉」。この色は、炊きあがったごはんの白さを引き立て、食材の色を際立たせてくれるんですよ。
困難を乗り越え、最高のパートナーと生み出した逸品
morita:開発は順調に進んだのでしょうか?
yamanaka:実は、最大の壁は開発を始める前にありました。
近年、土鍋の原料である「ペタライト」という鉱物が不足しており、そもそも土鍋を生産できる窯元さん自体が限られていたんです。
そんな中、最高のパートナーとなってくださったのが、以前からお付き合いのあった信楽焼の窯元「ヤマ庄陶器」さんでした。ペタライトを保有しているだけでなく、私たちのわがままな要望にも「ぜひやりましょう!」と応えてくださったんです。
【窯元 ヤマ庄陶器さんより】
「取っ手の平らな形状は、陶器の特性上、乾燥段階で切れやすく、バランスを取るのにとても苦労しました。また、本体の底の厚みや内側のカーブにもこだわり、どうすればもっと美味しくごはんを炊けるかを追求しました。
温かみのある信楽焼の『和』に、少し『洋』のテイストを加えて。伝統の中に新しさを感じるこのデザインが受け入れられるか不安もありましたが、今では私たちの自信作です。にちにち道具さんのエッセンスが加わり、さらに素晴らしいものができたと自負しています。」
ヤマ庄さんの技術と情熱がなければ、この土鍋は生まれませんでした。
morita:試作品での炊飯テストも大変だったのでは?
yamanaka: 8回、いえ10回以上は炊きましたね(笑)。実は私自身、それまで炊飯器でしかごはんを炊いたことがなくて…。自分好みの炊き加減を見つけるまで、浸水時間や水の量、火にかける時間を少しずつ変えて、まるで実験のようでした。
でも、初めて蓋を開けた時に「カニ穴」(※)ができていた時の感動は、今でも忘れられません!
(※カニ穴:ごはんが美味しく炊けた証拠。水蒸気が通った跡がカニの巣穴のように見えることから)

あなただけの「最高のごはん」を見つける楽しさ
morita:yamanakaさんにとって、このごはん鍋はどんな存在ですか?
yamanaka: 私一人の想いだけでなく、ヤマ庄陶器さん、デザインチーム、関わってくれたみんなの力が結集して生まれた、特別な存在です。最終サンプルが手元に届いた時は、心から「嬉しい!」と思いました。
morita:おすすめの炊き方や食べ方はありますか?
yamanaka: 実は、今でも「実験」は続いているんです(笑)。使うお米の品種や採れた時期によってもベストな水分量や加熱時間は変わるので、「正解はこれ!」という決まりはありません。
それこそが、このごはん鍋の醍醐味。いろいろな水量や時間を試して、ご自身の「最高のごはん」を見つけてほしいです。ちなみに、炊きあがりのタイミングから1分ほど加熱を延長すると、香ばしい「おこげ」が作れます。これも土鍋のごはん鍋ならではの楽しみですよね。
------------------------------------------------------------------
基本の炊き方:
①お米を洗米し、浸水させる。
※ごはん鍋で洗米・浸水は行わないでください。割れ・欠けの原因となります。
②お米をごはん鍋に入れ、中強火で約15分程度加熱する。
③蒸気が勢いよく出始めてから約2分程度待つ。
④蒸気が収まり始めたら火を止め、蓋を取らずに約15~20分程度蒸らす。
【浸水時間の目安】夏:30分/冬:1時間
※季節やお米の状態によって浸水時間が異なります。
【炊飯する際の水の目安】
1合(150g):180~250㎖
2合(300g):360~400㎖
3合(450g):540~650㎖
※浸水時間やお米の状態・お好みの硬さによって調整してください。
------------------------------------------------------------------

憧れだった「土鍋ごはん」を、もっと手軽に
morita:このごはん鍋をどんな方に使ってほしいですか?
yamanaka:「土鍋ごはんには憧れるけど、火加減の調整とか難しそうで、なかなか挑戦できなかった」という方にこそ、ぜひ手に取っていただきたいです。
にちにち道具のごはん鍋は、難しい火加減の調整は必要ありません。
土鍋のもともと熱の伝わりは遅いですが、一度温まったらなかなか冷めないという性質、そして底を厚くし、対流を考えた形状にしていることから、ずっと同じ中強火の火加減で大丈夫です。
しかも重みがあり、高さがある独特の蓋の形と3つ穴のおかげで、吹きこぼれの心配もほぼありません。
比較的簡単に土鍋ならではのふっくらおいしいごはんを炊く体験ができるんです。
morita:なるほど!それは心強いですね!
yamanaka:最後に、窯元さんからお聞きした、さらにおいしく炊く裏技をお伝えしますね。
炊くときに氷を5粒ほど入れると甘みが増すらしいです!私も知りませんでしたので、今度やってみたいと思っています。
この土鍋が、皆さんの食卓に寄り添い、日々の暮らしを少しだけ豊かにする。そんな存在になれたら、これ以上嬉しいことはありません。
morita:最後にこれからの「にちにち道具」について一言お願いします。
yamanaka:にちにち道具は、『にほんの四季や旬を大切にまいにちの家族との温かい食卓を大切に、そして一にち一にち自分を大切にする”丁寧なくらし”をつくる』をテーマに商品をご用意しております。
普段使いしやすい道具から、季節ごとにあった台所道具など、毎日の台所仕事がちょっと特別になるようなアイテムをこれからも開発して参りますので楽しみにしていてください。
■関連記事
【初心者さん大歓迎】憧れの鍋炊きご飯に挑戦!美味しい二つのごはん鍋。
この記事で紹介した商品